Column

子育て中のママ必見「よだれジミ 」や「ミルクの吐き戻し汚れ」の洗い方| お洗濯 の基本を学ぶ
赤ちゃんは母乳やミルクを吐き戻したり、よだれが出たりするので、衣類を頻繁に汚しますよね。 ミルク染みは、洗濯してもなかなか落ちないので、汚れたまま使っていたり、汚れがひどくなると捨ててしまう事も。 そこで今回は、赤ちゃんとの生活で切り離せない「吐き戻し汚れ」「よだれ汚れ」の基本的な洗い方をご紹介します。 ベビー服やスタイの黄色いシミの正体は? 赤ちゃん特有の汚れである吐き戻し汚れやよだれ汚れがついた跡が、黄色いシミになるのはなぜでしょうか? その正体は、母乳やミルクに含まれているタンパク質や炭水化物、脂質なのです。 タンパク質は時間が経つと固まり、脂質は空気と触れて酸化することによって黄色に変色するという性質を持っています。そのため、ベビー服やスタイ についた赤ちゃんの吐き戻した母乳やミルク、よだれは、しっかり洗い落とさないと固く黄色いシミとなってしまうのです。 ミルク染みはなぜ落としにくい? よだれの中には、歯を育てるカルシウムが含まれています。カルシウムはコンクリートにも含まれる成分で、汚れを繊維に固着させやすいという特徴があります。 ミルク染みを防ぐためには、なるべく早く汚れを落とすことがポイントになります。 時間が経ったミルク染みの場合、汚れが繊維に固着しているため、1度洗うだけでは落とし切れないことがあります。この場合、何度かつけ置き洗いを重ね、固着した汚れを少しずつ、繊維から剥がしていくことが大切です。 赤ちゃんのミルクや母乳の吐き戻し汚れ・よだれジミの洗濯方法 黄色いシミになってしまったベビー服やスタイを綺麗にするのは、手間がかかりますよね。ましてや、赤ちゃんのお世話をしている中、シミ抜きに時間をかけていられません。 でも、母乳やミルクに含まれるタンパク質は時間が経つと固まり、繊維に固着するという性質があります。汚れがついたスタイが乾燥してしまうと、落としづらい汚れになってしまうため、赤ちゃんが吐き戻したら、できるだけすぐに洗うことが大切です。 すぐに洗えない時は、まずつけ置き洗いを 吐き戻しやミルク染みで汚れてしまった時、まずおすすめしたいのが「つけ置き洗い」です。黄ばみの原因となるタンパク質汚れを分解し、繊維への固着を防ぎ、浮かせて落としましょう。 つけ置き洗いは面倒? いえいえ、実はとても簡単なんです!お湯に洗剤を溶かして、衣類をつけ置きするのにかかる時間はたった数十秒。洗濯機にかけるのは、時間のある時で大丈夫なので、1晩つけ置きして、他の洗濯物と一緒に翌朝洗うこともできます。 手間をかけずに汚れをしっかり落とせるつけ置き洗いは、忙しい方にこそ試していただきたい洗濯術です。 ミルクや母乳の吐き戻しの汚れを落とす手順 40℃程のお湯に、Rinenna#1(またはアルカリ性粉末洗剤)をよく溶かす 汚れている面を下にし、1~2時間ほどつけ置き洗いする 洗浄液ごと洗濯機に入れ、洗濯機で洗う 手順を動画で見る 汚れ落ちがUPするコツ 洗剤をお湯にしっかり溶かしましょう 洗濯機にかける際は、衣類量を減らし、8割以下で洗濯しましょう すすぎは必ず2回以上に設定しましょう 注意点...
子育て中のママ必見「よだれジミ 」や「ミルクの吐き戻し汚れ」の洗い方| お洗濯 の基本を学ぶ
赤ちゃんは母乳やミルクを吐き戻したり、よだれが出たりするので、衣類を頻繁に汚しますよね。 ミルク染みは、洗濯してもなかなか落ちないので、汚れたまま使っていたり、汚れがひどくなると捨ててしまう事も。 そこで今回は、赤ちゃんとの生活で切り離せない「吐き戻し汚れ」「よだれ汚れ」の基本的な洗い方をご紹介します。 ベビー服やスタイの黄色いシミの正体は? 赤ちゃん特有の汚れである吐き戻し汚れやよだれ汚れがついた跡が、黄色いシミになるのはなぜでしょうか? その正体は、母乳やミルクに含まれているタンパク質や炭水化物、脂質なのです。 タンパク質は時間が経つと固まり、脂質は空気と触れて酸化することによって黄色に変色するという性質を持っています。そのため、ベビー服やスタイ についた赤ちゃんの吐き戻した母乳やミルク、よだれは、しっかり洗い落とさないと固く黄色いシミとなってしまうのです。 ミルク染みはなぜ落としにくい? よだれの中には、歯を育てるカルシウムが含まれています。カルシウムはコンクリートにも含まれる成分で、汚れを繊維に固着させやすいという特徴があります。 ミルク染みを防ぐためには、なるべく早く汚れを落とすことがポイントになります。 時間が経ったミルク染みの場合、汚れが繊維に固着しているため、1度洗うだけでは落とし切れないことがあります。この場合、何度かつけ置き洗いを重ね、固着した汚れを少しずつ、繊維から剥がしていくことが大切です。 赤ちゃんのミルクや母乳の吐き戻し汚れ・よだれジミの洗濯方法 黄色いシミになってしまったベビー服やスタイを綺麗にするのは、手間がかかりますよね。ましてや、赤ちゃんのお世話をしている中、シミ抜きに時間をかけていられません。 でも、母乳やミルクに含まれるタンパク質は時間が経つと固まり、繊維に固着するという性質があります。汚れがついたスタイが乾燥してしまうと、落としづらい汚れになってしまうため、赤ちゃんが吐き戻したら、できるだけすぐに洗うことが大切です。 すぐに洗えない時は、まずつけ置き洗いを 吐き戻しやミルク染みで汚れてしまった時、まずおすすめしたいのが「つけ置き洗い」です。黄ばみの原因となるタンパク質汚れを分解し、繊維への固着を防ぎ、浮かせて落としましょう。 つけ置き洗いは面倒? いえいえ、実はとても簡単なんです!お湯に洗剤を溶かして、衣類をつけ置きするのにかかる時間はたった数十秒。洗濯機にかけるのは、時間のある時で大丈夫なので、1晩つけ置きして、他の洗濯物と一緒に翌朝洗うこともできます。 手間をかけずに汚れをしっかり落とせるつけ置き洗いは、忙しい方にこそ試していただきたい洗濯術です。 ミルクや母乳の吐き戻しの汚れを落とす手順 40℃程のお湯に、Rinenna#1(またはアルカリ性粉末洗剤)をよく溶かす 汚れている面を下にし、1~2時間ほどつけ置き洗いする 洗浄液ごと洗濯機に入れ、洗濯機で洗う 手順を動画で見る 汚れ落ちがUPするコツ 洗剤をお湯にしっかり溶かしましょう 洗濯機にかける際は、衣類量を減らし、8割以下で洗濯しましょう すすぎは必ず2回以上に設定しましょう 注意点...

洗濯機・洗濯槽の汚れがごっそり取れる掃除方法!汚れの原因やきれいに保つポイントも解説
4児の母で洗濯研究家の平島 利恵です。みなさんは洗濯機を、どのくらいの頻度で掃除していますか?洗濯槽の掃除は、「洗濯物に黒いカス(黒カビ)がついたら」という方もいらっしゃるかもしれません。でも、それでは遅すぎるんです…!「黒カビが衣類につく」ということは、洗濯槽裏に黒カビが大繁殖している証拠。洗濯をしたのに洋服が臭うという方も、洗濯槽裏の黒カビが影響している可能性があります。では、なぜ洗濯槽には黒カビが繁殖しやすいのでしょうか。今回は、洗濯槽に付着する汚れとその落とし方、洗濯槽の黒カビを予防する普段の使い方・お手入れ方法について詳しく解説をします。 洗濯機の汚れとは? 毎日洗剤を使って洋服を洗濯する洗濯機は、一見綺麗なように見えますよね?でも実は、洗濯機は見えない部分に汚れが蓄積しやすく、その汚れをエサにし、黒カビが繁殖しやすい環境です。洗濯機につく汚れは、どのようなものがあるのでしょうか。 石けんカス 石けんカスとは、水道水に含まれるミネラル分(カルシウム・マグネシウムなど)と、皮脂などの油汚れ・石けんに含まれる脂肪酸が結合したものです。 油・脂肪酸が水中のミネラルと結合して発生するため、石けん成分が配合されていない洗剤をお使いでも、皮脂と水があれば発生するのが石けんカスです。 石けんカスは、油分を多く含む汚れなので水は溶けません。また、水より比重が軽いため、水面にプカプカと浮きます。身体を洗ったタオルをすすいだ際に、浮く白いものを「アカ」だと思っている方も多いと思いますが、実はあれが石けんカスなのです。 石けん洗剤をお使いの方は、石けんカスに要注意 石けんカスは、油・脂肪酸が水中のミネラルと結合して発生しますが、石鹸洗剤の原料は、天然油脂もしくは脂肪酸のため、合成洗剤と比べて石けんカスが発生しやすい特徴があります。 洗濯槽裏に残った石けんカスは、黒カビのエサとなり、繁殖を招くため、石けん洗剤をお使いの場合は、1~2週間に1度の高頻度で洗濯槽の掃除を心がけると安心です。 ホコリ 洗濯機は外側にも内側にも埃が蓄積します。 脱衣所に洗濯機がある場合、衣類の着脱により空気中に舞うホコリが洗濯機の外側、洗濯機の壁との隙間、防水パンなどに蓄積します。 洗濯機の内側には、洗濯の際に出た糸くず(ホコリ)が蓄積します。糸くずフィルターで洗濯中のホコリをキャッチしますが、掃除を怠るとホコリが洋服に再付着してしまいます。糸くずフィルターに溜まったゴミは濡れた状態です。そのまま放置すると、洗濯槽内の黒カビの温床にもなります。 水アカ ミネラルウォーターと同じように、水道水にもミネラル分(ケイ素、カルシウムなど)が含まれています。洗濯槽に残った水滴は蒸発しますが、ミネラル分はその場に残り、白っぽくこびりついてしまいます。 皮脂汚れ 洗濯の際、洋服についた皮脂汚れは洗剤の力で洗濯槽の水の中に溶け出します。すすぎ不足で汚れが残った状態で脱水を行うと、洗濯槽裏にすすぎ残した皮脂汚れが付着してしまいます。 洗剤・柔軟剤残り 洗剤や柔軟剤を規定量以上入れると、余剰成分が洗濯槽裏に付着し、蓄積します。特に柔軟剤は、すすぎの一番最後の水に混ぜて投入され、そのまま脱水するため、計量せずに適当に入れると、余分な柔軟剤成分がそのまま洗濯槽裏に残ってしまいます。 カビ 上記の、石けんカス、ホコリ、洗剤・柔軟剤残り、皮脂などをエサに洗濯槽裏には黒カビが繁殖します。湿度が高く、エサとなる汚れが蓄積しがちな洗濯機は黒カビにとって絶好の環境です。洗濯槽裏だけでなく、自動投入口や洗剤ケースの裏、糸くずフィルターなどあらゆる場所に黒カビが発生します。 意外かもしれませんが、田舎の綺麗な水(浄水器をつけなくてもおいしい水が飲める地域)の方が、洗濯槽のカビが繁殖しやすいといわれています。塩素処理をそれほどしなくてもよい綺麗な水だからこそ、逆に洗濯槽にカビが繁殖しやすくなるのです。 洗濯機を掃除しないと汚れが衣類につく可能性も 掃除をしていない洗濯槽裏は、黒カビだらけです。汚れた洗濯槽で洋服を洗濯をしていたら…当然洗濯物に雑菌・黒カビが付着します。 出したばかりの洗濯物から嫌なニオイがする 洗濯物に黒いカスがつく というお悩みも、実は洗濯槽裏の黒カビが原因なんです。 洗濯もに黒いワカメ(黒カビ)が付着するようになってから洗濯槽クリーナーを使う方もいますが、黒カビがはがれてくる=洗濯槽裏は黒カビだらけということなんです。...
洗濯機・洗濯槽の汚れがごっそり取れる掃除方法!汚れの原因やきれいに保つポイントも解説
4児の母で洗濯研究家の平島 利恵です。みなさんは洗濯機を、どのくらいの頻度で掃除していますか?洗濯槽の掃除は、「洗濯物に黒いカス(黒カビ)がついたら」という方もいらっしゃるかもしれません。でも、それでは遅すぎるんです…!「黒カビが衣類につく」ということは、洗濯槽裏に黒カビが大繁殖している証拠。洗濯をしたのに洋服が臭うという方も、洗濯槽裏の黒カビが影響している可能性があります。では、なぜ洗濯槽には黒カビが繁殖しやすいのでしょうか。今回は、洗濯槽に付着する汚れとその落とし方、洗濯槽の黒カビを予防する普段の使い方・お手入れ方法について詳しく解説をします。 洗濯機の汚れとは? 毎日洗剤を使って洋服を洗濯する洗濯機は、一見綺麗なように見えますよね?でも実は、洗濯機は見えない部分に汚れが蓄積しやすく、その汚れをエサにし、黒カビが繁殖しやすい環境です。洗濯機につく汚れは、どのようなものがあるのでしょうか。 石けんカス 石けんカスとは、水道水に含まれるミネラル分(カルシウム・マグネシウムなど)と、皮脂などの油汚れ・石けんに含まれる脂肪酸が結合したものです。 油・脂肪酸が水中のミネラルと結合して発生するため、石けん成分が配合されていない洗剤をお使いでも、皮脂と水があれば発生するのが石けんカスです。 石けんカスは、油分を多く含む汚れなので水は溶けません。また、水より比重が軽いため、水面にプカプカと浮きます。身体を洗ったタオルをすすいだ際に、浮く白いものを「アカ」だと思っている方も多いと思いますが、実はあれが石けんカスなのです。 石けん洗剤をお使いの方は、石けんカスに要注意 石けんカスは、油・脂肪酸が水中のミネラルと結合して発生しますが、石鹸洗剤の原料は、天然油脂もしくは脂肪酸のため、合成洗剤と比べて石けんカスが発生しやすい特徴があります。 洗濯槽裏に残った石けんカスは、黒カビのエサとなり、繁殖を招くため、石けん洗剤をお使いの場合は、1~2週間に1度の高頻度で洗濯槽の掃除を心がけると安心です。 ホコリ 洗濯機は外側にも内側にも埃が蓄積します。 脱衣所に洗濯機がある場合、衣類の着脱により空気中に舞うホコリが洗濯機の外側、洗濯機の壁との隙間、防水パンなどに蓄積します。 洗濯機の内側には、洗濯の際に出た糸くず(ホコリ)が蓄積します。糸くずフィルターで洗濯中のホコリをキャッチしますが、掃除を怠るとホコリが洋服に再付着してしまいます。糸くずフィルターに溜まったゴミは濡れた状態です。そのまま放置すると、洗濯槽内の黒カビの温床にもなります。 水アカ ミネラルウォーターと同じように、水道水にもミネラル分(ケイ素、カルシウムなど)が含まれています。洗濯槽に残った水滴は蒸発しますが、ミネラル分はその場に残り、白っぽくこびりついてしまいます。 皮脂汚れ 洗濯の際、洋服についた皮脂汚れは洗剤の力で洗濯槽の水の中に溶け出します。すすぎ不足で汚れが残った状態で脱水を行うと、洗濯槽裏にすすぎ残した皮脂汚れが付着してしまいます。 洗剤・柔軟剤残り 洗剤や柔軟剤を規定量以上入れると、余剰成分が洗濯槽裏に付着し、蓄積します。特に柔軟剤は、すすぎの一番最後の水に混ぜて投入され、そのまま脱水するため、計量せずに適当に入れると、余分な柔軟剤成分がそのまま洗濯槽裏に残ってしまいます。 カビ 上記の、石けんカス、ホコリ、洗剤・柔軟剤残り、皮脂などをエサに洗濯槽裏には黒カビが繁殖します。湿度が高く、エサとなる汚れが蓄積しがちな洗濯機は黒カビにとって絶好の環境です。洗濯槽裏だけでなく、自動投入口や洗剤ケースの裏、糸くずフィルターなどあらゆる場所に黒カビが発生します。 意外かもしれませんが、田舎の綺麗な水(浄水器をつけなくてもおいしい水が飲める地域)の方が、洗濯槽のカビが繁殖しやすいといわれています。塩素処理をそれほどしなくてもよい綺麗な水だからこそ、逆に洗濯槽にカビが繁殖しやすくなるのです。 洗濯機を掃除しないと汚れが衣類につく可能性も 掃除をしていない洗濯槽裏は、黒カビだらけです。汚れた洗濯槽で洋服を洗濯をしていたら…当然洗濯物に雑菌・黒カビが付着します。 出したばかりの洗濯物から嫌なニオイがする 洗濯物に黒いカスがつく というお悩みも、実は洗濯槽裏の黒カビが原因なんです。 洗濯もに黒いワカメ(黒カビ)が付着するようになってから洗濯槽クリーナーを使う方もいますが、黒カビがはがれてくる=洗濯槽裏は黒カビだらけということなんです。...

実は汚れがべったり!?テーマパークのカチューシャを正しく洗って清潔に長く楽しもう!洗い方をプロが解説
4児の母で洗濯研究家の平島 利恵です。テーマパークへのお出かけの定番と言えば、カチューシャですよね!1日楽しく過ごした後、カチューシャはお手入れしていますか?たった1日とはいえ、普段よりアクティブに過ごすテーマパークで使ったカチューシャには皮脂や汗がたっぷり染み込んでいるです。ニオイや変色が起こる前に、汚れをしっかり落として保管しましょう! ユニバ(USJ)やディズニーなどのテーマパークカチューシャ、洗えるの? テーマパークのカチューシャは、洗濯しない方が多いと思います。でも多くのカチューシャは洗うことができるんです。 見た目はキレイに見えても、頭に一日中付けていると頭皮から出る汗・皮脂や、化粧品・日焼け止めなどの汚れが付着しています。汚れがついたまま保管してしまうと、次に使う時に黄ばみや色褪せ、臭いが気になることも。使用後は洗って保管する習慣をつけましょう! 洗えるカチューシャと洗えないカチューシャを見分ける 洗濯機で洗えるもの ヘアバンド 被り物 手洗いで洗えるもの カチューシャ プラスチックが使われているもの 繊細な装飾がついているもの 洗わないほうがよいもの スパンコールなどでできているもの 合皮・革など、洗えない素材でできているもの 特殊な塗装がされているもの カチューシャなど、プラスチックが使われているものを洗濯機にかけると、折れてしまう可能性があります。つけ置き洗いで優しく汚れを落としましょう! 色落ちチェックをお忘れなく 染色が甘いものは、濃度の高い洗浄液でつけ置き洗いをすると色落ちしてしまうことがあります。カチューシャには様々なパーツが使われているので、本体ではなく、パーツや刺繍糸が色落ちすることも。 色落ちが心配なもの・鮮やかな色のものは、目立たない場所に洗剤をつけ、5分ほど待ったあとタオルで拭き、色落ちしていないか確認しましょう。 汚れ別!洗えるカチューシャの洗い方 洗濯機で洗えるヘアバンドや被り物は、洗濯ネットに入れておしゃれ着コースで洗濯するだけでOKです。洗濯機で洗えず手洗いをするものは、Rinennaでつけ置き洗いをしましょう! 汗や皮脂汚れが気になるときは 暑い日にテーマパークで1日中着けていたカチューシャや、過去に使ったものでいざ使おうと出してみたら、なんだかニオイや黄ばみが気になる・・というカチューシャは、Rinenna#1のつけ置き洗いで、染み込んだ汗・皮脂汚れをスッキリ落としましょう。 手順 Rinenna#1を40℃のお湯によく溶かします しっかり沈め、30分ほどつけ置き洗いします 水を入れかえ、泡が出なくなるまで、よくすすぎます...
実は汚れがべったり!?テーマパークのカチューシャを正しく洗って清潔に長く楽しもう!洗い方をプロが解説
4児の母で洗濯研究家の平島 利恵です。テーマパークへのお出かけの定番と言えば、カチューシャですよね!1日楽しく過ごした後、カチューシャはお手入れしていますか?たった1日とはいえ、普段よりアクティブに過ごすテーマパークで使ったカチューシャには皮脂や汗がたっぷり染み込んでいるです。ニオイや変色が起こる前に、汚れをしっかり落として保管しましょう! ユニバ(USJ)やディズニーなどのテーマパークカチューシャ、洗えるの? テーマパークのカチューシャは、洗濯しない方が多いと思います。でも多くのカチューシャは洗うことができるんです。 見た目はキレイに見えても、頭に一日中付けていると頭皮から出る汗・皮脂や、化粧品・日焼け止めなどの汚れが付着しています。汚れがついたまま保管してしまうと、次に使う時に黄ばみや色褪せ、臭いが気になることも。使用後は洗って保管する習慣をつけましょう! 洗えるカチューシャと洗えないカチューシャを見分ける 洗濯機で洗えるもの ヘアバンド 被り物 手洗いで洗えるもの カチューシャ プラスチックが使われているもの 繊細な装飾がついているもの 洗わないほうがよいもの スパンコールなどでできているもの 合皮・革など、洗えない素材でできているもの 特殊な塗装がされているもの カチューシャなど、プラスチックが使われているものを洗濯機にかけると、折れてしまう可能性があります。つけ置き洗いで優しく汚れを落としましょう! 色落ちチェックをお忘れなく 染色が甘いものは、濃度の高い洗浄液でつけ置き洗いをすると色落ちしてしまうことがあります。カチューシャには様々なパーツが使われているので、本体ではなく、パーツや刺繍糸が色落ちすることも。 色落ちが心配なもの・鮮やかな色のものは、目立たない場所に洗剤をつけ、5分ほど待ったあとタオルで拭き、色落ちしていないか確認しましょう。 汚れ別!洗えるカチューシャの洗い方 洗濯機で洗えるヘアバンドや被り物は、洗濯ネットに入れておしゃれ着コースで洗濯するだけでOKです。洗濯機で洗えず手洗いをするものは、Rinennaでつけ置き洗いをしましょう! 汗や皮脂汚れが気になるときは 暑い日にテーマパークで1日中着けていたカチューシャや、過去に使ったものでいざ使おうと出してみたら、なんだかニオイや黄ばみが気になる・・というカチューシャは、Rinenna#1のつけ置き洗いで、染み込んだ汗・皮脂汚れをスッキリ落としましょう。 手順 Rinenna#1を40℃のお湯によく溶かします しっかり沈め、30分ほどつけ置き洗いします 水を入れかえ、泡が出なくなるまで、よくすすぎます...

父の日ギフトに最適な洗剤特集!加齢臭対策や汗染み対策もできる洗剤がおすすめ!
父の日に洗剤を贈る理由とは? 実用的で喜ばれるプレゼント 父の日といえば、ネクタイやお酒などの定番のプレゼントが思い浮かぶかもしれません。しかし、近年では、お父さんの毎日をもっと快適に、そして楽しくしてくれる洗剤が人気を集めています。洗剤が父の日ギフトに選ばれる理由は、毎日使うものだから、必ず喜んでもらえるという点が挙げられます。お父さんは毎日洗濯をするものです。だからこそ、毎日使うたびに、あなたの感謝の気持ちを思い出してもらえるでしょう。さらに、洗剤は消耗品なので、気兼ねなく贈れるという点も魅力です。ネクタイやお酒などの高価なプレゼントは、お父さんの好みがわからない場合、悩んでしまったり、せっかくプレゼントしてもお蔵入りになることも。洗剤であれば、気兼ねなく贈れるので、義理のお父さんへのプレゼントにもおすすめです。当店では、お父さんへのプレゼントにぴったりのオリジナル洗濯洗剤を豊富に用意しています。お父さんの好みやライフスタイルに合わせた洗剤を、ぜひお選びください。父の日に、お父さんへの感謝の気持ちを、毎日の暮らしに溶け込むギフトで伝えましょう。 クサイ、と言われないお父さんに! お父さんって、つい油断するとちょっとニオイが…なんてことはありませんか? そんなお父さんへのプレゼントに、ニオイ対策のできる洗剤はもってこいなんです。 さりげなく、お父さんのニオイをケアできます。ニオイをケアすることで、お父さんの自信を高めることができますし、自分の父が「クサイ」と言われていると思うと...悲しいですよね。 Rinennaではお父さんへのプレゼントにぴったりな「くさいニオイをごっそり落とす、洗濯洗剤・Rinenna#2」がご好評いただいております。 自分では買わないような高品質な洗剤を贈るメリット 高品質な洗剤は、洗濯結果が格段に向上したり、衣類を長持ちさせたりといったメリットがあります。 高品質な洗剤は、洗浄力が高く、汚れをしっかり落とすことができますし、衣類の繊維を傷めずに洗い上げることができます。また、色落ちや型崩れを防ぐ効果も期待できます。 今まで体験したことのない、汚れ落ちや、タイパで、感動体験を送ることができますよ。 父の日におすすめの洗剤の選び方 お父さんの好みに合わせた香りの選び方 お父さんへのプレゼントに、洗剤を贈りたいけど、どんな香りが喜んでもらえるか迷う…そんなあなたへ、お父さんの香りの好みに合わせた洗剤の選び方をご紹介します。 お父さんの好きな香りのアイテムを参考に選ぶ 香水やヘアコロンを使っている場合や、アロマオイルをよく使っている場合は、その香りに近い洗剤を選ぶと良いでしょう。 お父さんのライフスタイルを参考に選ぶ お父さんの好きな香りに見当がつかない場合は、お父さんのライフスタイルを参考に選んでみましょう。 一般的なライフスタイルから連想される香りを記載しておきますので是非参考になさってくださいね。 アウトドア派のお父さんには: 爽やかな柑橘系やミント系の香り 仕事柄スーツを着るお父さんには: 上品な石鹸系やフローラル系の香り インドア派のお父さんには: ラベンダーやカモミールなどのハーブ系の香り お父さんに直接聞いてみる お父さんに直接「どんな香りの洗剤が好き?」と聞いてみましょう。 普段聞かないような質問をすることでお父さんの意外な一面を知ることができる機会になるかもしれません。 ...
父の日ギフトに最適な洗剤特集!加齢臭対策や汗染み対策もできる洗剤がおすすめ!
父の日に洗剤を贈る理由とは? 実用的で喜ばれるプレゼント 父の日といえば、ネクタイやお酒などの定番のプレゼントが思い浮かぶかもしれません。しかし、近年では、お父さんの毎日をもっと快適に、そして楽しくしてくれる洗剤が人気を集めています。洗剤が父の日ギフトに選ばれる理由は、毎日使うものだから、必ず喜んでもらえるという点が挙げられます。お父さんは毎日洗濯をするものです。だからこそ、毎日使うたびに、あなたの感謝の気持ちを思い出してもらえるでしょう。さらに、洗剤は消耗品なので、気兼ねなく贈れるという点も魅力です。ネクタイやお酒などの高価なプレゼントは、お父さんの好みがわからない場合、悩んでしまったり、せっかくプレゼントしてもお蔵入りになることも。洗剤であれば、気兼ねなく贈れるので、義理のお父さんへのプレゼントにもおすすめです。当店では、お父さんへのプレゼントにぴったりのオリジナル洗濯洗剤を豊富に用意しています。お父さんの好みやライフスタイルに合わせた洗剤を、ぜひお選びください。父の日に、お父さんへの感謝の気持ちを、毎日の暮らしに溶け込むギフトで伝えましょう。 クサイ、と言われないお父さんに! お父さんって、つい油断するとちょっとニオイが…なんてことはありませんか? そんなお父さんへのプレゼントに、ニオイ対策のできる洗剤はもってこいなんです。 さりげなく、お父さんのニオイをケアできます。ニオイをケアすることで、お父さんの自信を高めることができますし、自分の父が「クサイ」と言われていると思うと...悲しいですよね。 Rinennaではお父さんへのプレゼントにぴったりな「くさいニオイをごっそり落とす、洗濯洗剤・Rinenna#2」がご好評いただいております。 自分では買わないような高品質な洗剤を贈るメリット 高品質な洗剤は、洗濯結果が格段に向上したり、衣類を長持ちさせたりといったメリットがあります。 高品質な洗剤は、洗浄力が高く、汚れをしっかり落とすことができますし、衣類の繊維を傷めずに洗い上げることができます。また、色落ちや型崩れを防ぐ効果も期待できます。 今まで体験したことのない、汚れ落ちや、タイパで、感動体験を送ることができますよ。 父の日におすすめの洗剤の選び方 お父さんの好みに合わせた香りの選び方 お父さんへのプレゼントに、洗剤を贈りたいけど、どんな香りが喜んでもらえるか迷う…そんなあなたへ、お父さんの香りの好みに合わせた洗剤の選び方をご紹介します。 お父さんの好きな香りのアイテムを参考に選ぶ 香水やヘアコロンを使っている場合や、アロマオイルをよく使っている場合は、その香りに近い洗剤を選ぶと良いでしょう。 お父さんのライフスタイルを参考に選ぶ お父さんの好きな香りに見当がつかない場合は、お父さんのライフスタイルを参考に選んでみましょう。 一般的なライフスタイルから連想される香りを記載しておきますので是非参考になさってくださいね。 アウトドア派のお父さんには: 爽やかな柑橘系やミント系の香り 仕事柄スーツを着るお父さんには: 上品な石鹸系やフローラル系の香り インドア派のお父さんには: ラベンダーやカモミールなどのハーブ系の香り お父さんに直接聞いてみる お父さんに直接「どんな香りの洗剤が好き?」と聞いてみましょう。 普段聞かないような質問をすることでお父さんの意外な一面を知ることができる機会になるかもしれません。 ...

帽子の汗染み・黄ばみが復活!洗濯研究家が教える、家庭でできる正しい洗い方【キャップ・ハット対応】
4児の母で洗濯研究家の平島 利恵です。 夏の帽子、気づくと白い汗染みが浮いていたり、昨年の帽子を出したら黄ばんで「もう捨てるしかない…」と思った経験、ありませんか? 汗や皮脂、日焼け止めの成分は、時間が経つと繊維にこびりついて変色します。でも実は、帽子の汗染みも、正しい方法でお洗濯すればきれいに復活できるんです。 家庭の洗濯機で洗えるものも多く、正しい方法を知れば、意外と簡単。汗をたっぷりかいた日は、放置せずに“洗ってリセット”するのがおすすめです。蓄積汚れを防ぐことで、変色を予防し、帽子のもちもぐっと長くなります。 この記事では、「帽子を洗っても黄ばみが残る」「型崩れが怖くて洗えない」そんなお悩みを解消するプロの洗い方を詳しくお伝えします。 帽子の汗染み・黄ばみはなぜ落ちないの? 汗の99%は水分です。 でも残り1%に含まれるタンパク質・皮脂・ミネラルが、繊維の奥に入り込み、酸化することで黄ばみや白い輪ジミを作ります。 汗の“酸化”が進むと、時間が経ってから黄ばみが浮き出てくるのです。 一方で、夏の強い紫外線は生地の染料を分解・退色させます。特に紺・黒・緑などの濃色帽子では、汗成分と紫外線が反応し、色素が変性して褪せたように見えることも。 つまり、帽子の汗染みや色褪せは、「酸化した汚れ」+「紫外線による染料の変化」が重なって起こる、非常に厄介な現象なのです。 擦らず、もみ洗いせず。Rinennaなら、つけ置くだけ 「帽子の汗染みや黄ばみは自分では落とせない」と感じる方も多いですが、正しい洗剤と温度・時間のコツをつかめば、ご家庭でもプロの仕上がりが目指せます。 実は、酸化したタンパク質汚れは一般的な洗剤では分解しきれず、洗濯をしても黄ばみが残ってしまいます。 それをブラシなどでゴシゴシこすると、繊維を傷める原因に。 そこで試してほしいのが、皮脂・汗汚れにフォーカスした洗剤「Rinenna#1」。 たんぱく質分解酵素をふんだんに配合し、繊維の奥に蓄積した汗の汚れやニオイを、しっかり浮かせて落とします。 「もみ洗いをせず、つけ置くだけ」——手間をかけなくても、綺麗が蘇る。 忙しい方にこそ試してほしい、Rinennaの洗濯です。 実際に黄ばんだ帽子をRinennaで洗うと… Rinennaのつけ置き洗いで、黄ばんでいた帽子が蘇りました。 >動画で見る 【プロ直伝】帽子の汗染み・黄ばみを家庭で落とす洗い方 用意するもの Rinenna#1(または汗のニオイが強い場合はRinenna#2) バケツまたは洗面器 ゴム手袋 40℃前後のお湯 洗濯機洗いの手順...
帽子の汗染み・黄ばみが復活!洗濯研究家が教える、家庭でできる正しい洗い方【キャップ・ハット対応】
4児の母で洗濯研究家の平島 利恵です。 夏の帽子、気づくと白い汗染みが浮いていたり、昨年の帽子を出したら黄ばんで「もう捨てるしかない…」と思った経験、ありませんか? 汗や皮脂、日焼け止めの成分は、時間が経つと繊維にこびりついて変色します。でも実は、帽子の汗染みも、正しい方法でお洗濯すればきれいに復活できるんです。 家庭の洗濯機で洗えるものも多く、正しい方法を知れば、意外と簡単。汗をたっぷりかいた日は、放置せずに“洗ってリセット”するのがおすすめです。蓄積汚れを防ぐことで、変色を予防し、帽子のもちもぐっと長くなります。 この記事では、「帽子を洗っても黄ばみが残る」「型崩れが怖くて洗えない」そんなお悩みを解消するプロの洗い方を詳しくお伝えします。 帽子の汗染み・黄ばみはなぜ落ちないの? 汗の99%は水分です。 でも残り1%に含まれるタンパク質・皮脂・ミネラルが、繊維の奥に入り込み、酸化することで黄ばみや白い輪ジミを作ります。 汗の“酸化”が進むと、時間が経ってから黄ばみが浮き出てくるのです。 一方で、夏の強い紫外線は生地の染料を分解・退色させます。特に紺・黒・緑などの濃色帽子では、汗成分と紫外線が反応し、色素が変性して褪せたように見えることも。 つまり、帽子の汗染みや色褪せは、「酸化した汚れ」+「紫外線による染料の変化」が重なって起こる、非常に厄介な現象なのです。 擦らず、もみ洗いせず。Rinennaなら、つけ置くだけ 「帽子の汗染みや黄ばみは自分では落とせない」と感じる方も多いですが、正しい洗剤と温度・時間のコツをつかめば、ご家庭でもプロの仕上がりが目指せます。 実は、酸化したタンパク質汚れは一般的な洗剤では分解しきれず、洗濯をしても黄ばみが残ってしまいます。 それをブラシなどでゴシゴシこすると、繊維を傷める原因に。 そこで試してほしいのが、皮脂・汗汚れにフォーカスした洗剤「Rinenna#1」。 たんぱく質分解酵素をふんだんに配合し、繊維の奥に蓄積した汗の汚れやニオイを、しっかり浮かせて落とします。 「もみ洗いをせず、つけ置くだけ」——手間をかけなくても、綺麗が蘇る。 忙しい方にこそ試してほしい、Rinennaの洗濯です。 実際に黄ばんだ帽子をRinennaで洗うと… Rinennaのつけ置き洗いで、黄ばんでいた帽子が蘇りました。 >動画で見る 【プロ直伝】帽子の汗染み・黄ばみを家庭で落とす洗い方 用意するもの Rinenna#1(または汗のニオイが強い場合はRinenna#2) バケツまたは洗面器 ゴム手袋 40℃前後のお湯 洗濯機洗いの手順...
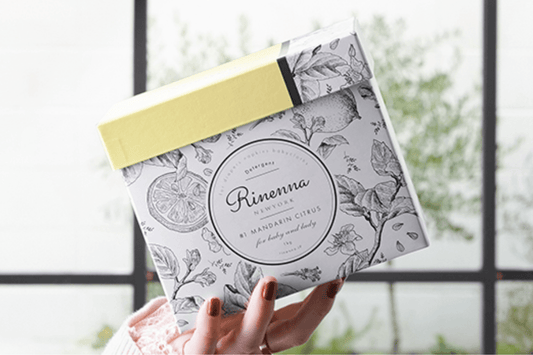
Rinennaを作ろうと思った理由と開発秘話
Rinenna洗剤を作ろうと思った理由 布おむつの商品開発と販売 第一子の育児休暇中に、東日本大震災が起こりました。その時私・平島は神奈川県に住んでいましたが、首都圏では紙おむつを含むの日用品の買い占めが起こり、 街中から紙おむつが姿を消していました。困り果て、棚の隅に残っていた布おむつを買ったところからRinenna(旧名称:Estlance)は始まりました。 初めて使った布おむつは、ゴミも出ず、素材も優しく、赤ちゃんもなんだか気持ちがよさそう。汚れたらこまめにおむつ交換をするようにもなり、赤ちゃんとのコミュニケーションも増え、いいことばかりだなと思いました。 でも当時、主に流通していたのは「布おむつカバー」と「輪おむつ」でした。布おむつカバーのサイズを選び間違え、赤ちゃんの身体と合わずに漏れてしまったり、洗濯機の中で輪おむつが絡まるのが不便だったり、 デザインが好みでなかったり…もっとママたちが快適に、心地よく使える布おむつを作りたいと思うようになり、布おむつの開発を始めました。 布おむつをご購入くださったお客様からのメール Webでコツコツ売り始め、売上も伸びてきた頃、突然お客様からこんなメールが・・・ 「うつになりました 布おむつを洗濯して、洗濯して、 もみ洗いする毎日に疲れて うつになりました。 いい商品だったけど、断念します。 いろいろアドバイスいただいてありがとうございました。」 自分が納得できる布おむつを開発し、本当に良いものを届けていたつもりだったのに、 お母さんに負担をかけてしまったことが、本当にショックでした。 それと同時に、やっぱりもみ洗いって面倒臭いし、汚れたおむつを手で触るのって嫌だよなとも思いました。 はじまりは布おむつ リネンナという洗濯洗剤は、元々手がけていた「布おむつ」がきっかけで生まれました。布おむつのハードルはなんと言っても「汚してしまった後の処理=洗濯」ですよね。赤ちゃんのお肌に良い事は分かっているけれど、「自分では清潔に保てるのかが心配」「手洗いなど手間がかかる」などがネックになり、布おむつに手を出せずにいたり、挫折してしまう…というご意見も多かったんです。布おむつは汚れてしまったら、汚物を丁寧に取り除き→もみ洗いをして→洗濯機 というのが一般的な工程です。赤ちゃんのあいだは、ミルクや夜泣き、離乳食の準備やお散歩…etc. ただでさえママの毎日は大忙しなのに、オムツ替えの度にその処理をしなければならないなんて…。それでも、「赤ちゃんのために」という想いで、紙おむつより断然手間暇のかかる布おむつを使うママのために出来る事はないか?頑張るママをもっと楽にしてあげたい。そんな想いからこの洗濯洗剤の開発がスタートしました。 もみ洗い無しで汚れを落とせる洗剤を作りたい! もみ洗いしても【汚れが】 落ちない現象をどうにかしたい!! そもそも【もみ洗いなし】で汚れが落ちる洗剤ってないの? つけ置きだけで汚れが落ちたら最高!!!! と、 洗剤の原料屋さんと「もみ洗いなしでウンチを落とせる洗剤」の開発が始まります。...
Rinennaを作ろうと思った理由と開発秘話
Rinenna洗剤を作ろうと思った理由 布おむつの商品開発と販売 第一子の育児休暇中に、東日本大震災が起こりました。その時私・平島は神奈川県に住んでいましたが、首都圏では紙おむつを含むの日用品の買い占めが起こり、 街中から紙おむつが姿を消していました。困り果て、棚の隅に残っていた布おむつを買ったところからRinenna(旧名称:Estlance)は始まりました。 初めて使った布おむつは、ゴミも出ず、素材も優しく、赤ちゃんもなんだか気持ちがよさそう。汚れたらこまめにおむつ交換をするようにもなり、赤ちゃんとのコミュニケーションも増え、いいことばかりだなと思いました。 でも当時、主に流通していたのは「布おむつカバー」と「輪おむつ」でした。布おむつカバーのサイズを選び間違え、赤ちゃんの身体と合わずに漏れてしまったり、洗濯機の中で輪おむつが絡まるのが不便だったり、 デザインが好みでなかったり…もっとママたちが快適に、心地よく使える布おむつを作りたいと思うようになり、布おむつの開発を始めました。 布おむつをご購入くださったお客様からのメール Webでコツコツ売り始め、売上も伸びてきた頃、突然お客様からこんなメールが・・・ 「うつになりました 布おむつを洗濯して、洗濯して、 もみ洗いする毎日に疲れて うつになりました。 いい商品だったけど、断念します。 いろいろアドバイスいただいてありがとうございました。」 自分が納得できる布おむつを開発し、本当に良いものを届けていたつもりだったのに、 お母さんに負担をかけてしまったことが、本当にショックでした。 それと同時に、やっぱりもみ洗いって面倒臭いし、汚れたおむつを手で触るのって嫌だよなとも思いました。 はじまりは布おむつ リネンナという洗濯洗剤は、元々手がけていた「布おむつ」がきっかけで生まれました。布おむつのハードルはなんと言っても「汚してしまった後の処理=洗濯」ですよね。赤ちゃんのお肌に良い事は分かっているけれど、「自分では清潔に保てるのかが心配」「手洗いなど手間がかかる」などがネックになり、布おむつに手を出せずにいたり、挫折してしまう…というご意見も多かったんです。布おむつは汚れてしまったら、汚物を丁寧に取り除き→もみ洗いをして→洗濯機 というのが一般的な工程です。赤ちゃんのあいだは、ミルクや夜泣き、離乳食の準備やお散歩…etc. ただでさえママの毎日は大忙しなのに、オムツ替えの度にその処理をしなければならないなんて…。それでも、「赤ちゃんのために」という想いで、紙おむつより断然手間暇のかかる布おむつを使うママのために出来る事はないか?頑張るママをもっと楽にしてあげたい。そんな想いからこの洗濯洗剤の開発がスタートしました。 もみ洗い無しで汚れを落とせる洗剤を作りたい! もみ洗いしても【汚れが】 落ちない現象をどうにかしたい!! そもそも【もみ洗いなし】で汚れが落ちる洗剤ってないの? つけ置きだけで汚れが落ちたら最高!!!! と、 洗剤の原料屋さんと「もみ洗いなしでウンチを落とせる洗剤」の開発が始まります。...

洗剤と柔軟剤の使い方を間違えると衣類にどんな影響が?正しい方法とポイント解説
洗剤と柔軟剤を間違えた!このまま洗っても大丈夫? 洗濯の時、うっかり洗剤と柔軟剤を入れ間違えてしまったことはありませんか? そんな時、そのまま洗濯を続けても大丈夫なのでしょうか?「柔軟剤入り洗剤」も発売されていますが、洗剤と柔軟剤なぜ投入口が分かれているのでしょうか。 実は、洗剤と柔軟剤はそれぞれ全く異なる役割を持っているんです。 今回は、洗剤と柔軟剤の違いと、間違えてしまった場合の対処法について詳しく解説します。 この記事では、以下の内容についてお伝えします。 洗剤と柔軟剤の役割と成分の違い 洗剤と柔軟剤を間違えて投入した場合の影響 間違えた場合の正しい対処法と予防策 洗濯の時には、洗剤と柔軟剤を正しく使い分けることが大切です。間違えてしまったらどうなるのか、ぜひこの記事を読んで確認してください。 洗剤と柔軟剤の投入口を間違えた時どうする? 洗濯機にかけるとき、洗剤と柔軟剤は、どのタイミングで投入されるのでしょうか。 投入されるタイミング 洗濯の工程 洗剤 初めの給水時 洗い 柔軟剤 最後のすすぎの水 すすぎ 洗剤は、一番初めの給水時に一緒に投入され、「洗い」の工程で、洗剤が混ざった洗浄液で、衣類を洗います。 一方柔軟剤は、一番最後のすすぎの水と一緒に投入され、「すすぎ」の工程で、柔軟剤が入った水ですすぐことで衣類を柔らかく仕上げます。 このように、「洗剤」と「柔軟剤」が投入される工程は、全く違うのです。 そのため、間違って入れてしまうと、どちらの効果も十分に発揮することができなくなり、すすぎ直しが必要になるケースもあります。 洗剤を柔軟口に入れてしまった場合の対処法 洗剤を柔軟剤口に入れてしまうと、一番最後のすすぎの水に、洗剤が投入されてしまうことになります。 洗濯前に気付いた時 柔軟剤ケースを出し、中を空にし、ケースに残った洗剤成分をしっかり洗い流してから元に戻します。 洗濯中に気付いた時...
洗剤と柔軟剤の使い方を間違えると衣類にどんな影響が?正しい方法とポイント解説
洗剤と柔軟剤を間違えた!このまま洗っても大丈夫? 洗濯の時、うっかり洗剤と柔軟剤を入れ間違えてしまったことはありませんか? そんな時、そのまま洗濯を続けても大丈夫なのでしょうか?「柔軟剤入り洗剤」も発売されていますが、洗剤と柔軟剤なぜ投入口が分かれているのでしょうか。 実は、洗剤と柔軟剤はそれぞれ全く異なる役割を持っているんです。 今回は、洗剤と柔軟剤の違いと、間違えてしまった場合の対処法について詳しく解説します。 この記事では、以下の内容についてお伝えします。 洗剤と柔軟剤の役割と成分の違い 洗剤と柔軟剤を間違えて投入した場合の影響 間違えた場合の正しい対処法と予防策 洗濯の時には、洗剤と柔軟剤を正しく使い分けることが大切です。間違えてしまったらどうなるのか、ぜひこの記事を読んで確認してください。 洗剤と柔軟剤の投入口を間違えた時どうする? 洗濯機にかけるとき、洗剤と柔軟剤は、どのタイミングで投入されるのでしょうか。 投入されるタイミング 洗濯の工程 洗剤 初めの給水時 洗い 柔軟剤 最後のすすぎの水 すすぎ 洗剤は、一番初めの給水時に一緒に投入され、「洗い」の工程で、洗剤が混ざった洗浄液で、衣類を洗います。 一方柔軟剤は、一番最後のすすぎの水と一緒に投入され、「すすぎ」の工程で、柔軟剤が入った水ですすぐことで衣類を柔らかく仕上げます。 このように、「洗剤」と「柔軟剤」が投入される工程は、全く違うのです。 そのため、間違って入れてしまうと、どちらの効果も十分に発揮することができなくなり、すすぎ直しが必要になるケースもあります。 洗剤を柔軟口に入れてしまった場合の対処法 洗剤を柔軟剤口に入れてしまうと、一番最後のすすぎの水に、洗剤が投入されてしまうことになります。 洗濯前に気付いた時 柔軟剤ケースを出し、中を空にし、ケースに残った洗剤成分をしっかり洗い流してから元に戻します。 洗濯中に気付いた時...

新生児布おむつ育児の始め方:基本から実践までの徹底解説と私の体験
こんにちは、Rinenna スタッフのMadokaです♩ 5月20日に第一子を無事に出産しました!産後一ヶ月少しの時間が過ぎ、やっと初めての育児に少ーしずつではありますが 慣れつつあります。 この記事では、産後ママのリアル育児と布おむつについて綴っていきたいと思います✩ 布おむつ育児、開始! さてさて 産前からとっても楽しみにしていた布おむつ育児。 退院後、早速生後5日の新生児のうちからの布おむつ育児をスタートさせました* 布おむつカバーは 新生児から使えるフリーサイズを購入 サイズ調整も細かくきくので、まだ3200gほどの我が子にも ぴったりフィットしてくれました♡ このモコモコ感がたまらない〜(´ω`)♡ このたまらなく可愛い我が子のモコモコ姿が見られるのは 布おむつ育児をしてるママの特権ですね♡♡ 頻繁すぎる・・、新生児の布おむつ交換 よーし!布おむつ育児頑張るぞ!! と張り切ったのも束の間、、、 布おむつ育児は 思っていたより簡単な反面、地味に面倒でした。 「簡単」 というのも、布おむつは紙おむつと違って うんちやおしっこをすると赤ちゃんが泣いて教えてくれるので、おむつ替えのタイミングもとっても分かりやすい✧ 替えた後は つけ置き用バケツにポイポイ入れてって、翌朝お洗濯機に入れるだけ。成型タイプの布おむつなので干すのも簡単、畳まずにバスケットに重ねて入れていくだけ。 「全然簡単やないかーい!!!」 それが布おむつ育児を始めた当初の私の率直な感想でした。 が。 が!!!...
新生児布おむつ育児の始め方:基本から実践までの徹底解説と私の体験
こんにちは、Rinenna スタッフのMadokaです♩ 5月20日に第一子を無事に出産しました!産後一ヶ月少しの時間が過ぎ、やっと初めての育児に少ーしずつではありますが 慣れつつあります。 この記事では、産後ママのリアル育児と布おむつについて綴っていきたいと思います✩ 布おむつ育児、開始! さてさて 産前からとっても楽しみにしていた布おむつ育児。 退院後、早速生後5日の新生児のうちからの布おむつ育児をスタートさせました* 布おむつカバーは 新生児から使えるフリーサイズを購入 サイズ調整も細かくきくので、まだ3200gほどの我が子にも ぴったりフィットしてくれました♡ このモコモコ感がたまらない〜(´ω`)♡ このたまらなく可愛い我が子のモコモコ姿が見られるのは 布おむつ育児をしてるママの特権ですね♡♡ 頻繁すぎる・・、新生児の布おむつ交換 よーし!布おむつ育児頑張るぞ!! と張り切ったのも束の間、、、 布おむつ育児は 思っていたより簡単な反面、地味に面倒でした。 「簡単」 というのも、布おむつは紙おむつと違って うんちやおしっこをすると赤ちゃんが泣いて教えてくれるので、おむつ替えのタイミングもとっても分かりやすい✧ 替えた後は つけ置き用バケツにポイポイ入れてって、翌朝お洗濯機に入れるだけ。成型タイプの布おむつなので干すのも簡単、畳まずにバスケットに重ねて入れていくだけ。 「全然簡単やないかーい!!!」 それが布おむつ育児を始めた当初の私の率直な感想でした。 が。 が!!!...


